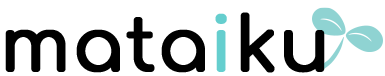「その日からすでに2ヶ月経ったんだ。彼女との出会いからね。でも、こんな結果を招くとは思わなかった…」
と、僕は自宅のリビングで親友の健太に打ち明けた。
「彼女との出会いはまるで映画のようだったよ。疲れて帰ると、優しく話しかけてくれる。まるで夢みたいだった。」
不倫の底に足を突っ込んでしまったことを、心の底から後悔している。
一緒にいられないパートナーから情熱的な恋人へ

「でも、なんでそんなことになったんだ?パートナーとは仲良さそうだったじゃないか」
と、健太が真剣な視線で問い詰める。
「うん、表面上はそう見えるだろう。でも、実はセックスレスだったんだ。最近では話すことすら減り、ただの同棲人みたいな感じ。それが彼女に出会ってしまった原因かもしれない。」
不倫の道を選んでしまったこと、それは全て自分の選択だ。
彼女に求められる喜び、一緒にいる時間、それは何もかもがパートナーとは違った。
「彼女と過ごした初めての夜は、言葉にできないほど素晴らしかったよ。」
と、僕は彼に打ち明けた。
「彼女の部屋に入ると、僕の心はドキドキして、一瞬で全てを感じ取ることができた。
彼女の温もり、彼女の香り、そして彼女の欲求。
それらが僕の体を包み込み、その瞬間、僕は彼女に溺れてしまった。」
僕の手はソファのクッションを固く握りしめ、僕の顔は熱を帯びていた。
「彼女の目は僕の全てを見つめて、僕を受け入れてくれた。彼女の唇が僕の唇に触れた瞬間、僕の心は彼女だけに捧げることを確信したよ。」
僕は次に彼女の手の感触について話し始めた。
「彼女の手は僕の体にソフトに触れ、僕を優しく包んだ。彼女に全てを触れられることで、初めて自分自身を全て解放できた。彼女と一緒に、快楽の世界へ飛び込んだんだ。」
「そして、彼女の愛撫が始まると、全てが焦燥感で包まれた。彼女の手が僕の体を探し、求める度に、僕の心は高鳴り、快楽へと駆け上がった。その時、僕は初めて彼女の中の女性と対面したんだ。」
僕はそこで話を終え、満足感と混ざった微笑みを浮かべた。
「あの夜以来、僕は彼女との関係について考えず、ただ彼女との時間を楽しんでいるだけ。でも、それが本当に正しいのかどうかはわからない。でも、あの瞬間の快感は、忘れられないよ。」
「でも、彼女が僕をどう思っているのか、それがわからなくて。本当に愛してくれているのか、それともただの遊びなのか。それに、パートナーと子供たちに対して罪悪感を感じてしまうんだ。」
僕の心情は複雑で、これからどうなるか予想もつかない。
次回、次の章へ…
あわせて読みたい