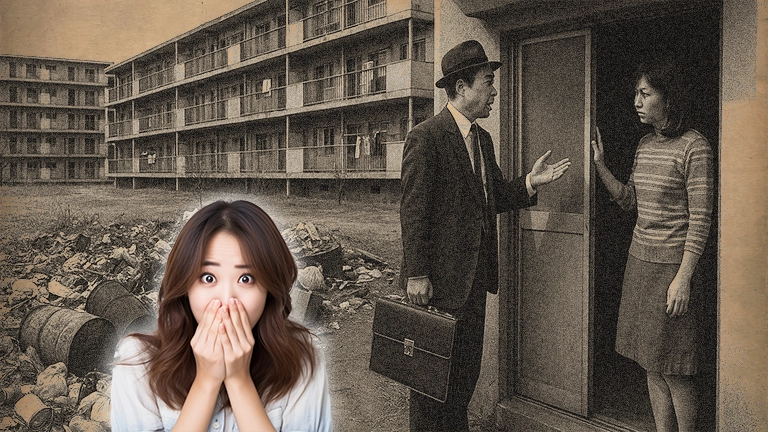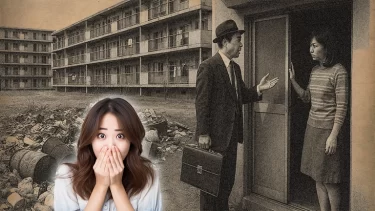令和の常識から見ると完全にありえない行動や光景が、昭和では当たり前のように存在していました。
今回は、その中でも特に「これはウソでしょ?」と思わず言いたくなるような昭和のリアルな日常風景を2つ紹介します。
令和生まれや平成育ちには衝撃的すぎる…その実態とは?
ゴミ問題は本当に地獄だった

現在では、家庭ごみは分別して指定された曜日に出し、回収された後は効率的に焼却・再利用されるのが当たり前の時代。
しかし、昭和30年代から40年代の「高度経済成長期」における日本は、まったく違う状況にありました。
経済が爆発的に発展し、家電やプラスチック製品が家庭に急速に普及した結果、家庭ごみの量も劇的に増加します。
しかし、当時のインフラはその急増にまったく対応できていなかったのです。
ごみ処理場の能力は限界を超え、焼却や埋立が追いつかずに、ごみが山のように積み上がり、街の空き地や山間部には不法投棄されたゴミが散乱していました。
最も恐ろしいのは衛生環境の悪化です。
ゴミの山にはハエやネズミが大量発生し、特に夏場は異臭と害虫の猛攻で、通学中の子どもがハエ叩きを持ち歩くというウワサが広まったほどです。
実際にハエが大量に発生していた学校では、教室にハエ叩きやハエ取り紙を常備していたという証言が残っています。
さらに、不法投棄によって近隣住民とのトラブルや自然環境の破壊も問題になり、ようやく昭和50年代以降にごみ処理法の整備やリサイクル意識が浸透し始めました。
今やエコが当たり前の令和世代からすれば、想像を絶する光景といえるでしょう。
昼間の主婦を狙った「押し売り」が日常
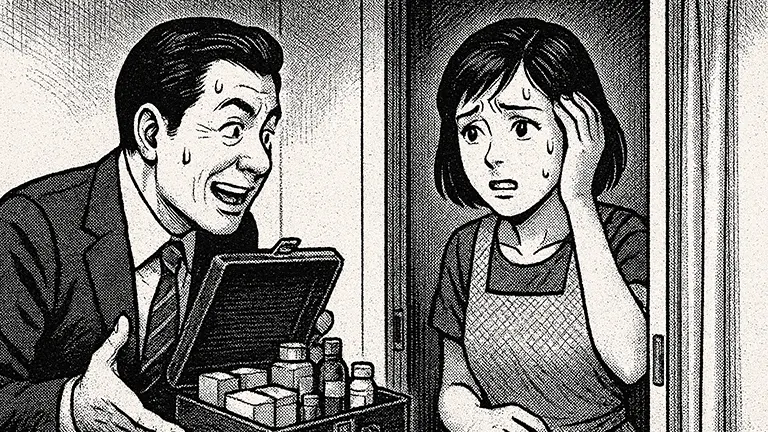
今の時代、いきなり知らない人が家を訪ねてきて、強引に物を売りつけてくるなんてことはまずありません。
訪問販売には厳しいルールがあり、クーリングオフ制度も充実しています。
しかし、昭和の中頃まではそんな制度も整っておらず、「押し売り」はほぼ無法地帯でした。
当時の家庭では、夫が会社に出勤し、昼間は専業主婦がひとりで家にいるケースが一般的で、そこを狙った押し売りたちが「奥さん、これ見て!いまどきこの値段では手に入らないよ!」と話しかけてくるのです。
売りに来るものは様々で、壺、掛け軸、布団、着物、調理器具など…。
どれも明らかに安物だったにもかかわらず、「これは〇〇の職人が手作りした逸品」「本日限りの特価」と嘘の付加価値をつけて高額販売する手口でした。
断ろうとすると、態度が急変し、「冷たい奥さんだな!」「買ってくれないと困る」と恫喝まがいのセールストークを繰り出すケースも多発、なかには「近所に聞こえるような声でわざと怒鳴り、主婦を心理的に追い詰めて買わせる」悪質な手口も存在しました。
昭和51年(1976年)に「訪問販売法」(現:特定商取引法)が制定され、こうした悪質な押し売り行為は次第に姿を消していきます。
現在ではそのような光景は考えられませんが、当時の主婦たちは本気で身の危険を感じていたのです。
まとめ
そんなのありえない!と思ってしまうような、信じがたい昭和の風景は、確かに存在していた日常でした。
今では信じられないようなことが、ほんの数十年前の現実だったという事実は、現代の私たちにとって貴重な教訓とも言えます。
昭和の闇を知ることで、令和のありがたみを再確認できるのではないでしょうか。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)