夏の甲子園と聞くと、炎天下の中で白球を追う球児たちの姿を思い浮かべる人は多いでしょう。
ここ数年、SNSやテレビの討論番組で必ず出るのが…「真夏の昼間に甲子園でやるのは危険じゃない?」「ドーム球場でやればいいじゃん」「せめてナイターにしてあげて…」こうした声は年々増えています。
確かに、40℃近い酷暑の中でのプレーは、熱中症やケガのリスクも高く、見ている側も心配になりますよね。
なぜドーム球場開催に踏み切らないのでしょうか?
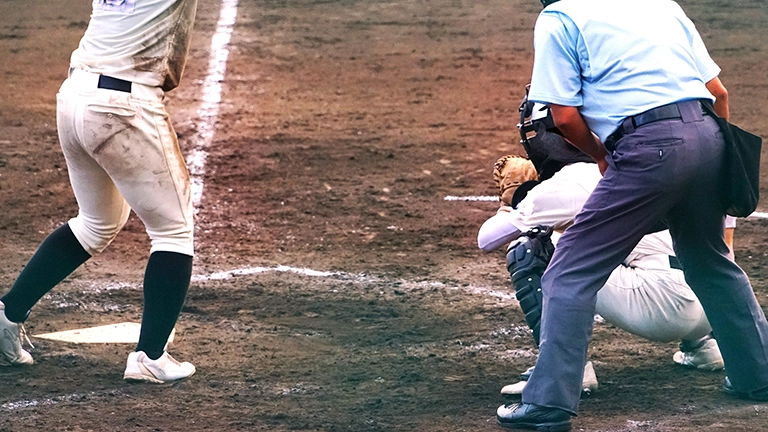
実はこの裏には、精神論や伝統だけでは片付けられない、かなり現実的で深い理由があるのです。
まず押さえておきたいのが、甲子園球場と高校野球の関係性です。
「高校野球の全国大会が甲子園で行われている」のではなく、正しくは「高校野球のために甲子園球場が建てられた」というのが本当の歴史です。
1915年に始まった全国中等学校野球大会(現在の夏の甲子園)は、当初は大阪の豊中球場で行われていました。
その後、阪神電鉄が鳴尾に新球場を建設し、第3回大会からそこで開催、観客がどんどん増え、「もっと大きな球場が必要だ!」となり、1924年に完成したのが甲子園球場です。
つまり、高校野球と甲子園はスタートから切っても切れない関係なのです。
しかも阪神電鉄は、この大会に関して球場使用料を一切取っていません。
これが後に大きな意味を持つことになります。
ドームでやればいいじゃん!の壁
例えば、京セラドーム大阪や東京ドームを丸々1日借りるとしましょう。
公式サイトでは時間貸し料金で、平日2200万円以上、土日なら2400万円以上、夏の甲子園は約15日間なので、単純計算でも数億円規模の出費になります。
一方、甲子園は使用料ゼロ円、その差は天と地どころか、地球と火星くらいの距離があります。
じゃあ放送権料やスポンサーで賄えば?と思うかもしれませんが、NHKの放送権料はなんと無料、理由は「高校生の部活動」であって、興行ではないからです。
入場料も既に上がっており、これ以上の値上げは現実的ではありません。
高校野球は、あくまで「教育の一環としての部活動」という位置づけです。
もしドーム開催のために高額な使用料を払うとなれば、その資金は入場料値上げやスポンサー料増額でまかなう必要が出てきます。
そうなると、もう完全に「プロの興行」と同じビジネス構造になってしまい、「教育」という建前が崩れてしまいます。
高野連の暑さ対策、実は進んでいる
近年の酷暑は本当に深刻、高野連も動き出しています。
2023年からは5回終了後に10分間の「クーリングタイム」を導入、2024年は午前と夕方に分ける「二部制」も実施されました。
さらに7イニング制への移行も検討中、ただし「野球の根幹を変える」と反対する声も根強く、慎重な議論が続いています。
「夏の甲子園」が甲子園で続く理由は、感情論や伝統論だけではありません。
- 球場使用料がゼロなのは甲子園だけ
- 全国からアクセスしやすい立地
- 宿泊施設の受け入れ体制
- 教育活動としての建前
- 阪神電鉄にとっても経済的メリットが大きい
これらがガッチリ噛み合っているため、他球場への移転は非現実的なのです。
だからこそ、高野連は「場所を変える」のではなく、「環境を改善して続ける」方向で動いているわけです。
まとめ
正直、猛暑の中でのプレーは見ていても心配になりますし、ドーム開催のほうが安全という意見も理解できます。
でも、現実的に考えると、甲子園以外で同じ規模・同じ条件の大会を開くのはほぼ不可能ではないでしょうか。
そして、その背景には、100年かけて積み上げられた経済的・歴史的な土台がしっかりある…それが今回の一番の「意外な理由」なのかもしれません。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)


