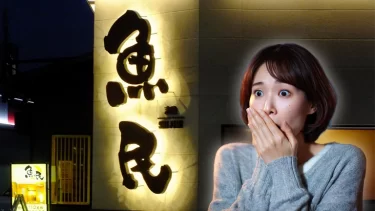魚民って、ワタミの系列じゃないの?そんな勘違いをしたことがある人、実は少なくないのではないでしょうか。
飲食業界の中でもパクリ戦略の象徴とまで言われた居酒屋チェーン「モンテローザ」、かつて2000店舗以上を展開し、一時代を築いたその巨大企業がいま閉店ラッシュに見舞われています。
なぜここまで衰退したのか?そして「名前が似すぎる」戦略の功罪とは…?
なぜ元祖パクリと呼ばれたのか?

モンテローザがパクリ企業と揶揄されるようになった背景には、他社に酷似した店名や業態を次々と展開した過去があります。
代表的な事例としては以下のようなものが挙げられます。
- 「魚民」 → ワタミの「和民」と1文字違い
- 「月の宴」 → 三光マーケティングフーズの「月の雫」との酷似
- 「山内農場」 → エー・ピーカンパニーの「塚田農場」にそっくり
- 「俺の串かつ黒田」 → 「俺のイタリアン」と「串カツ田中」の合わせ技のような名前
- 「雷ステーキ」 → 話題の「いきなり!ステーキ」にコンセプトが酷似
- 「寿司侍」 → 「寿司ざんまい」の印象を想起させるネーミング
モンテローザの手法は「他社が成功している業態に類似した店舗を素早く全国展開する」スタイルで、90年代から2000年代にかけて業界内で急成長を遂げました。
しかしその戦略が消費者の混乱や他社との対立を招き、訴訟沙汰になったケースも数多くあります。
モンテローザ黄金時代と拡大の軌跡
モンテローザのルーツは1975年、新宿・歌舞伎町にオープンした「モンテローガ」というパブレストランにあります。
1983年に株式会社モンテローザを設立し、同年には「白木屋中野南口駅前店」を開店します。
これがのちの「白木屋」1号店となります。
その後、90年代から2000年代にかけて、直営店方式を武器に急速に店舗網を拡大します。
1996年には300店舗を超え、1998年には売上1000億円を突破、2009年には1500店舗、そして2013年にはついに2000店舗の大台に到達します。
全国の主要駅前には「白木屋」「魚民」「笑笑」が並び、いわば駅前の顔とも言える存在となっていました。
閉店相次ぐ
2011年の東日本大震災時には、東北地方では約70店舗が一時休業を余儀なくされました。
関東では計画停電の影響で繁華街の灯りが消え客足は激減、企業の宴会や歓送迎会も次々と中止され、売上が半減した店舗も少なくなかったといいます。
また、同時期にブラック企業批判が高まり、業界全体のイメージ悪化にもつながります。
モンテローザでも2014年に従業員の過労死が報道され、残業代未払い問題なども明るみにでるなど、ネガティブ要因が重なります。
2017年には、ついに2000店舗を割り込む事態となりました。
そして、決定打となったのが新型コロナウイルスの流行です。
3密を避ける生活様式が推奨され、居酒屋業態そのものが危険な場所とされるようになり大打撃を受けます。
2023年時点で店舗数は約1228店とピーク時から800店舗近く減少しています。
これからのモンテローザ
モンテローザは、模倣によって市場を開拓し、大きな成長を遂げた企業でした。
しかし、時代は変わり業界全体が大きく縮小している中での再建は容易ではありません。
とはいえ、同社の機動力や実行力はこれまでも危機を乗り越える原動力となってきました。
模倣戦略からの脱却を果たし、新しい価値をどう創出できるかが、2025年以降の生き残りを左右することになりそうです。
まとめ
モンテローザは、模倣とスピード展開を武器に業界の頂点へと駆け上がった企業でした。
しかし、時代の価値観の変化や外的要因によって、今やその戦略が通用しない局面に差しかかっています。
真の意味での「改革」が求められる今、モンテローザがどのような道を選ぶのか、その一手に注目が集まっています。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)