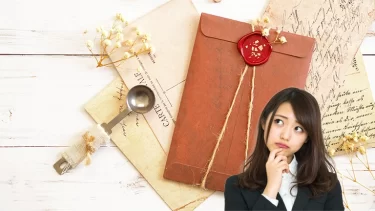昔の人が手紙の封に蝋を垂らしたり、「〆」と書いたりするのを見たことがありますか?
一見、ちょっとした飾りや形式に見えるこれらの行為には、実は深い意味と歴史が隠されています。
今回は、「封蝋(シーリングワックス)」と「〆印」の起源や役割、そして現代に受け継がれる美しい手紙の文化について紹介します。
封蝋は防犯と信頼の象徴
昔のヨーロッパでは、手紙を閉じる際に熱した蝋(ろう)を垂らし、その上に印章を押す「封蝋(ふうろう)」が使われていました。
これは単なる装飾ではなく、他人に中身を見られないようにするための防犯手段で、もし誰かが途中で手紙を開けようとすれば、蝋が割れてしまい受け取った人はすぐに不正を察知できます。
いわば昔の「セキュリティシール」のような役割を果たしていたのです。
また、押された印章には家や個人の紋章(シグネットリング)が使われ、「この手紙は確かに本人からのものだ」と証明する真正性の証拠にもなっていました。
特に貴族や王族、外交官たちはそれぞれ固有の紋章を持ち、その封印は社会的信用の象徴でもあったのです。
封蝋はまさに、信頼を封じる文化といえるでしょう。
日本の〆印、封じる心が生んだ文化
一方、日本では封蝋の代わりに「〆」という独特の記号が発展しました。
〆は、もともと漢字の「締(しめる)」の略字であり、きちんと封じる・終えるという意味を持ちます。
江戸時代の書簡では、以上・かしこなどの結語のあとに〆を書き加え、「ここで文は終わりです」「これ以上は書き足していません」という改ざん防止のサインとして使われていました。
さらに、明治時代に郵便制度が整うと、封筒の表面に〆印と書く慣習が定着、〆は日本版の簡易封蝋であり、送り手の誠実さを示す証拠でもありました。
時代が進み、現代では封筒にはあらかじめ糊がつくようになり、メールやLINEでのやりとりが主流になった現代では、封蝋や〆印の実用性はほとんど失われています。
しかし、「丁寧に封をする」という行為は、結婚式の招待状や誕生日カードなどに封蝋を使う人が増えています。
また、ビジネスシーンやフォーマルな手紙では、文末に〆を入れることで文面が引き締まり、礼を尽くした印象を与えます。
かつては改ざん防止のサインだった〆も、いまでは日本人らしい美意識と礼節の象徴として息づいているのです。
まとめ
封蝋も〆印も、もとは「封じる」ための実用的な工夫でしたが、その根底にあるのは相手を思いやる心や誠実さなのかもしれません。
たとえ電子メールが主流になっても、人の心を封じて届けたいという願いは変わりません。
封蝋の光沢や〆印の一文字には、そんな日本と世界に共通する伝える文化の温かさが、今も静かに息づいているのですね。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)