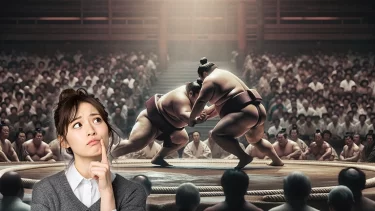お相撲さんのように体の大きな人が飛行機に乗るとき、航空会社には特別な対応があり、また相撲界には「大量の力士が同じ飛行機に乗らない」という独自のルールも存在します。
そこには単に座席の問題だけでなく、実は国技を守るためのリスク分散という深い理由が隠されています。
今回は、力士の飛行機利用にまつわる裏事情をわかりやすく紹介します。
座席に収まらない場合の航空会社の対応

体格の大きな人がエコノミー座席に座ると、1席に収まりきれないことがあります。
その場合、航空会社は「エクストラシート」と呼ばれる仕組みで対応しています。
これは、隣席を同じ乗客用として販売する制度で、追加料金を払えば2席分を確保できるというものです。
料金は航空会社によって異なりますが、一般的に 1.5倍から1.8倍程度の運賃で利用できるケースが多いです。
通常の2倍の料金を払うよりも割安で、広いスペースを確保できるため、力士や大柄なスポーツ選手だけでなく、快適さを求める一般乗客が利用することもあります。
なぜ力士は同じ飛行機に乗らないのか?
座席問題以上に興味深いのが、「相撲部屋の力士が一度に大量に飛行機に乗ることはない」という慣習です。
その背景には、安全と伝統を守るための強い意識があります。
第一の理由は「重量バランス」の問題です。
150kgを超える力士が何十人も同じ便に乗れば、機体の重心やバランスに影響を及ぼす可能性があります。
航空会社側も安全を最優先にするため、力士を複数の便に分散させることが望ましいのです。
第二の理由は「リスク分散」です。
もし一つの飛行機で事故が起きてしまった場合、その便に所属する部屋や一門の力士全員が一度に失われてしまう危険性があります。
相撲は日本の国技であり、長い歴史と文化を背負っています。
その担い手が一度に消えてしまうことを防ぐために、同じ便に集中して搭乗することは避けられているのです。
このリスク分散の思想は、相撲に限らず、歌舞伎役者の一門やスポーツチーム、さらには政治や皇室の移動にも共通して見られます。
文化や国を支える存在を一度に失わないための知恵といえるでしょう。
まとめ
お相撲さんが飛行機に乗る際には、座席に収まらない場合の「エクストラシート」制度や、ビジネスクラス利用などの工夫が行われています。
そして何より特徴的なのは、一度に大量の力士が同じ便に搭乗しないようにしていることです。
そこには、体格による安全面の配慮だけでなく、「国技としての相撲を絶やさない」という強い使命感が表れています。
私たちが空港や駅で力士を見かけたとき、その背後にはこうした深い理由があるのだと知れば、また違った視点で国技を身近に感じられるのではないでしょうか。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)