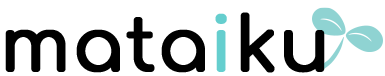2026年WBCで、侍ジャパンは予選ラウンドを無敗の全勝で突破し、世界連覇へ向けて順調なスタートを切りました。
しかし、今大会から導入された新システム「ピッチコム」に当初は苦戦していた日本代表ですが、意外な形で問題を解決します。
それが、日本の人気野球ゲーム「パワフルプロ野球(パワプロ)」の操作方式でした。
WBC、新ルール「ピッチコム」に侍ジャパンが苦戦していた
今回のWBCでは、サイン盗み防止や試合時間短縮を目的として、新しいサイン伝達システム「ピッチコム」が導入されました。
これはキャッチャーがボタンを押すことで球種やコースを音声で伝え、その内容がピッチャーの帽子に取り付けられた小型スピーカーに直接届く仕組みです。
従来のように指でサインを出す必要がなくなるため、メジャーリーグではすでに導入が進んでいる最新技術ですが、侍ジャパンにとってはこのシステムが思わぬ壁となりました。
ピッチコムには電卓のように9つのボタンが並び、球種やコースを選ぶために最大3回押す必要があります。
当初は球速の速い順にボタンが配置されていましたが、選手たちはその配置をなかなか覚えられず、試合中にボタンを探してしまうケースもあったといいます。
投球間にはピッチクロックという時間制限もあり、サイン交換が遅れると投球テンポにも影響します。
そこで、この状況を打開するアイデアを出したのが、阪神の捕手・坂本誠志郎選手でした。
救ったのはパワプロ配置という発想
坂本選手が提案したのは、人気野球ゲーム「パワフルプロ野球」の操作配置をそのままピッチコムに取り入れるというアイデアでした。
パワプロは1994年に発売されて以来、30年以上続く日本を代表する野球ゲームで、多くの野球少年がプレーしてきたため、その操作方法は世代を超えた共通言語ともいえます。
ゲームでは球種のボタン配置がシンプルで分かりやすく、例えば「上ボタン」はストレート系、「下ボタン」はフォーク系といったように、直感的に理解できるよう設計されています。
このパワプロ式の配置に変更したことで、捕手たちはボタンを探す必要がなくなり、瞬時にサインを送れるようになりました。
坂本選手自身も「手元を見てボタンを探す必要がなくなった。時間的な余裕ができた」と振り返っています。
さらに、ゲーム会社コナミも侍ジャパンを後押し、ピッチコムで流れる音声には「パワプロ」や「プロ野球スピリッツ」でおなじみの実況アナウンサーの音声が採用され、歓声や鳴り物が響く球場でも聞き取りやすいよう特別に調整された音源が提供されたのです。
実際の球場の環境音を参考にしながら音域やスピードを調整することで、大歓声の中でもクリアに聞こえるよう改良されました。
パワプロ世代の選手たちからも好評で、ロッテの種市篤暉選手は「言われてみれば確かに聞きやすい。懐かしい声ですね」と笑顔を見せたといいます。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)