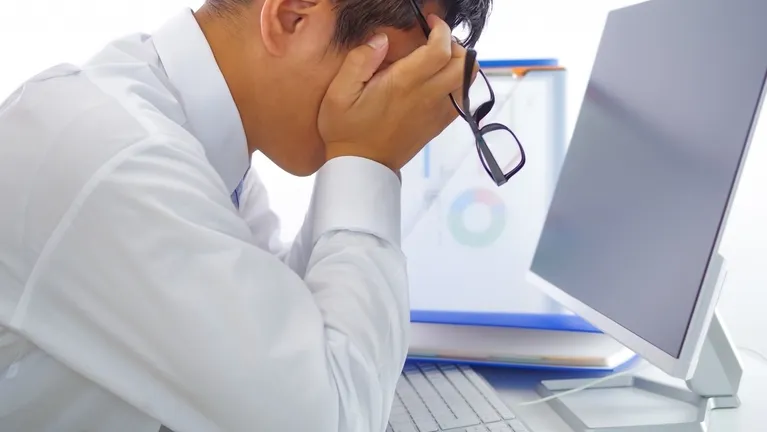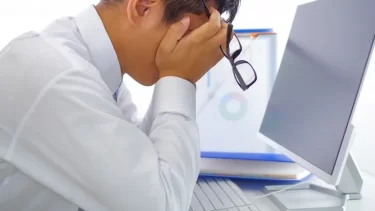ChatGPTやGemini、AIを活用したスケジュール管理ツール。
確かに仕事は速く進むようになりました。
でも便利になったはずなのに、なぜか毎日クタクタ。
チェックすべきテキストが山のように増え、目も心も張り詰めたまま。
そんな「便利なのにしんどい」違和感を抱えていませんか?
今、こうした状況を「AI疲れ」と呼ぶことが増えています。
この記事では、AI疲れの特徴とサイン、日常に取り入れたい小さな休息法、さらには漢方薬という選択肢まで、わかりやすくご紹介します。
増えている「AI疲れ」とは?
現代の働き方のなかでじわじわと広がっている「AI疲れ」。
まずはその特徴からみてみましょう。
AI疲れとは何か
AI疲れとは、生成AIを日常的に使うことで、慢性的な疲労感を感じる状態です。
たとえば、ChatGPTに文章を任せる機会が増えると、あっという間に文章が出来上がり、効率がアップ。
しかし、結果として膨大な数の文章をチェックすることにもつながります。
AIとの会話も、事務的・効率的な応答が主になり、感情や余白が削られていきます。
AI疲れが起こる背景
AI疲れが起こる背景には、以下のようなことが考えられます。
■情報量の急増
AIの提案や通知が次々と届き、脳にかかる情報処理量が一気に増大。
■心の切り替えタイミングの喪失
チャットのポップアップや自動リマインドが常にオン。
気を抜く暇がありません。
■感情表現の減少
AIの定型的な返信に慣れると、人との対話にも無機質さを感じやすくなります。
こうした要因が重なり、知らず知らずのうちに目・耳・心・頭に疲労が蓄積されていくのです。
「AI疲れ」のサインとは?
AI疲れは風邪のように「くしゃみ」や「熱」が出るわけではありません。
小さな異変を見逃さないことが大切です。
スクリーンタイムが長い
AI疲れにおいて見逃せないのが「スクリーンタイム」と「脳・心・目の疲れ」の関係です。
パーソル総合研究所の調査では、20代の正規雇用者(非管理職)において、1週間のスクリーンタイムが長い人ほど、脳疲労や眼精疲労が高く、ストレス
反応も強くなるという結果が出ています。(※1)
この傾向は30代以上でも同様であり、長時間の画面接触が、世代を問わずストレス状態と密接に関連していることが明らかになりました。
実際に、脳や目が疲れることでストレスがたまりやすくなることは、これまでの研究でもわかっています。
こんな変化は「AI疲れ」のサイン
こうした研究結果をふまえると、日々の業務でAIツールやチャットに接する時間が長い現代人にとって、以下のような変化はすでに“AI疲れ”のサインかもしれません。
- 画面を見ていると、目がショボショボする/乾く
- パソコンに向かっているだけなのに、肩・首が張ってくる
- 情報を処理し終えても、なぜか心が落ち着かない
- 休んでも頭が重く、朝からだるさが抜けない
こうした症状があるとき、「年齢のせいかな」「ちょっと忙しいだけ」と見過ごしがち。
しかし、実際には画面を通して脳と神経が過剰に刺激を受けている状態かもしれません。
AI疲れをためこまない生活習慣
AI疲れをやわらげるには、日常に“ちょっとした休息”を意識的に取り入れることが効果的です。
スマホ・ツールから意識的に離れる時間をつくる
1日のなかで、スマホやパソコンから離れて画面を見ない時間を設けましょう。
- 朝の通勤中、音楽だけ聞いて外の景色を楽しむ
- 昼休みにデスクを離れ、静かな場所で深呼吸する
- 寝る1時間前は通知をオフにして、読書やストレッチにあてる
こうした小さなデジタルデトックスが、心身の緊張をほぐすきっかけになります。
思考のアウトプットを増やす
また、AIに任せきりにしないために、自分の手と声を使う時間を増やすのも効果的です。
手書きのメモや日記をつけて、考えを形にする
同僚や家族と雑談の時間をつくり、感情のキャッチボールを楽しむ
カウンセリングを受けて自分の思考の癖に気づく
こうしたアウトプットが、感情や五感をリセットし、疲れた神経をほぐします。
AI疲れに漢方薬という選択肢も
生活習慣を整えても抜けない疲れには、からだの内側から改善を目指す漢方薬が有効です。
AI疲れの対策には、
- 血流をよくして目の周りの筋肉をゆるめる
- 水分の循環をよくしてドライアイを改善する
- 目に栄養を届けて目の疲れを軽減する
- 自律神経のバランスを整える
- 心をおだやかにし、気分の落ち込みやイライラを改善する
といった眼精疲労やストレスにアプローチできる漢方薬から選びます。
おすすめの漢方薬
- 杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)
目の使い過ぎによるドライアイ、眼精疲労のある方におすすめ。
飲む目薬ともいわれ、目に栄養を与えることで、かすみ目、疲れ目などに用いられます。
- 桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)
体力がなくて疲れやすく、神経過敏な方におすすめ。
精神を安定させることで自律神経を整え、不安や不眠、イライラに用いられます。
「どの漢方薬が自分に合うかわからない」という方は、オンラインの「あんしん漢方」を利用して、専門家に選んでもらうのがおすすめです。
薬剤師が、症状や体質に合わせて漢方薬を選んでくれるので、自宅にいながら安心してケアを始められます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
情報化とAI活用が進む一方で、脳も心もフル稼働し続ける毎日。
その結果としてあらわれる「AI疲れ」は、見過ごしがちな新しい不調です。
ストレスや目の疲れ、肩こりなどを感じたら、まずはデジタルデトックスとアウトプット習慣でリセットを。
それでも疲れが抜けないときは、漢方薬を取り入れることで、内側からのケアも検討してみてください。
AI時代を健やかに生き抜くには「効率」だけでなく、意識的な「休息」が欠かせません。
今日から少しずつ、自分に合った休息法を実践して、心とからだのバランスを取り戻しましょう。
参考文献
(※1)株式会社パーソル総合研究所 シンクタンク本部「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」2024
<この記事の監修者>

あんしん漢方(オンラインAI漢方)薬剤師|碇 純子(いかり すみこ)
薬剤師・元漢方薬生薬認定薬剤師 / 修士(薬学) / 博士(理学)
神戸薬科大学大学院薬学研究科、大阪大学大学院生命機能研究科を修了し、漢方薬の作用機序を科学的に解明するため、大阪大学で博士研究員として従事。現在は細胞生物学と漢方薬の知識と経験を活かして、漢方薬製剤の研究開発を行う。
世界中の人々に漢方薬で健康になってもらいたいという想いからオンラインAI漢方「あんしん漢方」で情報発信を行っている。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)