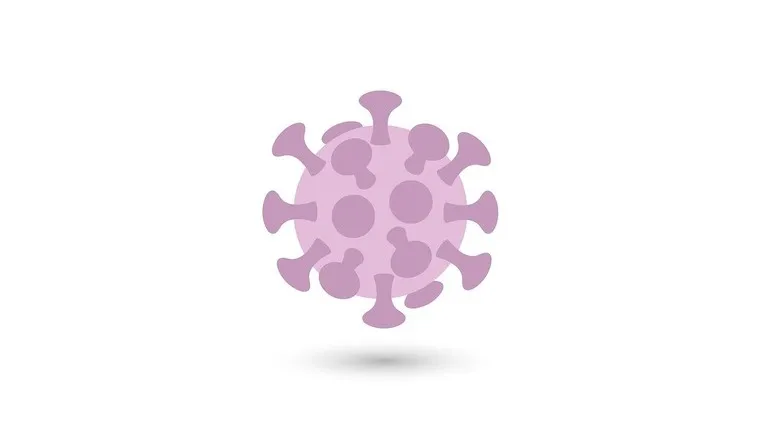冬になると毎年のように流行するインフルエンザ。
「マスクやワクチンで対策しているけれど、毎年なんとなく不安」「子どもが保育園でもらってきそう」「仕事が休めない」このようなお悩みは多いのではないでしょうか。
もちろん、予防接種や感染対策も大切ですが、もうひとつ意識しておきたいのが「かかりにくいからだづくり」です。
この記事では、免疫力という視点から、インフルエンザに負けない冬の過ごし方をわかりやすく解説します。
漢方薬という“体質ケア”の選択肢についてもご紹介していきます。
インフルエンザについての基礎知識
まずは、インフルエンザがどうやって広がるのか、どんな特徴があるのかをおさらいしましょう。
どうやって感染する?
インフルエンザは、インフルエンザウイルスという病原体が体内に入り、増殖することで発症します。
感染経路は、主に「飛沫感染」と「接触感染」です。
飛沫感染とは、感染者のくしゃみや咳などで飛び散ったウイルスを、口や鼻から吸い込んでしまうこと。
一方の接触感染は、ウイルスがついた手で目・鼻・口に触れることによって起こります。
発熱やのどの痛み、全身のだるさなどの症状が急激に出るのが特徴で、一般的な風邪よりも症状が重く、回復にも時間がかかることがあります。
なぜ冬に流行する?
インフルエンザは、毎年12月〜3月に流行するのが日本の傾向です。
その大きな理由は「低温・乾燥」というウイルスにとって都合のいい環境が整うから。
気温が低くなると、鼻やのどの粘膜の防御力が落ち、ウイルスが体内に入り込みやすくなります。
また、空気の乾燥によって飛沫が浮遊しやすくなり、遠くまでウイルスが届きやすくなるのです。
さらに、日照時間が短くなることにより、体内でのビタミンD生成量も減少。
ビタミンDは免疫力の維持の効果があるとされているため、冬は免疫力が落ちている可能性も指摘されています。
インフルエンザ対策は免疫力アップがカギ
ワクチンやマスクだけでは不安な人こそ「自分のからだの防御力」に目を向けてみましょう。
免疫力とは「からだを守る力」
免疫力とは、からだに入ってきたウイルスや細菌などの異物を見つけて攻撃し、からだを守る力のことです。
私たちのからだの中に存在する免疫細胞は、24時間体制で外敵からの侵入に備えています。
ただし、この免疫力は常に一定ではなく、加齢やストレス、睡眠不足、栄養の偏りなどで簡単に低下してしまいます。
「風邪をひきやすい」「疲れが抜けにくい」と感じる人は、免疫力が落ちているのかもしれません。
免疫力を保つ生活習慣とは
免疫力を高めるためには、毎日の生活習慣の見直しがとても大切です。
以下のポイントを意識してみましょう。
運動する
適度な運動は、血流をよくしてからだのさまざまな機能を高めるといわれています。
とくに、ウォーキングやストレッチ、ラジオ体操のような軽い運動は、からだへの負担も少なく、毎日の習慣に取り入れやすいのが魅力です。
睡眠をしっかりとる
免疫細胞は、睡眠中にメンテナンスされます。
夜更かしや不規則な生活はなるべく避けましょう。
バランスのとれた食事をする
たんぱく質・ビタミン・ミネラルを含む食品をまんべんなく摂ることで、免疫細胞の働きをサポートできます。
「一汁三菜」を意識して、さまざまな食材を摂れるよう献立を工夫しましょう。
腸内環境を整える
免疫細胞の多くが腸に集中しているため、腸活も重要です。
発酵食品や食物繊維を積極的に摂りましょう。
こうした積み重ねが、結果的に「かかりにくいからだ」につながっていきます。
からだの内側から整える「漢方薬」という選択肢
生活習慣の改善に加えて、体質そのものにアプローチできるのが「漢方薬」の魅力です。
東洋医学では「予防=からだづくり」
東洋医学では「病気になってから治す」より「病気にならないように整えて予防する」ことが大切だと考えます。
からだの不調は、免疫力が下がっているサインかもしれません。
「なんとなくだるい」「手足が冷える」「すぐに風邪をひく」といった症状がある人は、心とからだのバランスが崩れている可能性があります。
東洋医学では、その人の体質や体力、症状に合わせて処方を選び、内側からじっくり整えていきます。
とくに、免疫力を高めるには
- 自律神経のバランスを整え、ストレスによる疲労を減らし、睡眠の質を上げる
- 消化・吸収機能を改善することで内側から心とからだを元気にする
- 血流をよくしてからだ全体に栄養を届け、免疫力を高める
などの働きをもつ漢方薬を選ぶといいでしょう。
インフルエンザ対策におすすめの漢方薬
ここでは、からだが疲れやすいときに用いられる漢方薬とインフルエンザの初期症状や回復期に使われることがある代表的な漢方薬を紹介します。
- 麻黄湯(まおうとう)
インフルエンザの初期症状に用いられる漢方薬。
からだのふしぶしが痛み、寒気や高熱が出たときに使われます。
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
胃腸の働きを高めて気力を補い、疲労倦怠や食欲不振に用いられる漢方薬。
体力がない、疲れやすい、無気力で手足がだるいときに使われます。
- 竹茹温胆湯(ちくじょうんたんとう)
インフルエンザの回復期に用いられることもある漢方薬。
回復期に熱が長引いたり、平熱になっても気分がさっぱりせず、咳や痰が多くて眠れなかったりするときに使われます。
これらは一例であり、人によって合う処方は異なります。
漢方薬は「症状」だけでなく「体質」も考慮して選ぶことが大切です。
自分に合った漢方薬の見つけ方
「どの漢方薬が自分に合うのかわからない」──そんなときは、専門家に相談するのが安心です。
最近では、オンラインで漢方薬の相談・購入ができる「あんしん漢方」というサービスも注目されています。
スマホで体調や体質について質問に答えるだけで、AIと漢方薬の専門家が連携して、あなたに合った処方を選んでくれます。
しかも、自宅まで漢方薬が届くから、忙しい人や育児中の人にもぴったりです。
「体質から整える」インフルエンザ対策に、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
インフルエンザは、毎年のように流行する身近な感染症。
しかし「免疫力を高めて、かかりにくいからだをつくる」という視点を持つだけで、少し安心感が生まれます。
からだのバリア機能を整え、冷えや疲れをケアすることで、冬を元気に乗り越える準備ができます。
今年の冬は、外側の対策だけでなく「内側のケア」にも目を向けてみませんか?
気になる体質の悩みがある人は、漢方薬でじっくり整えるのもひとつの手です。
毎日を元気に過ごすために、自分のからだを守る力を少しずつ育てていきましょう。
<この記事の監修者>
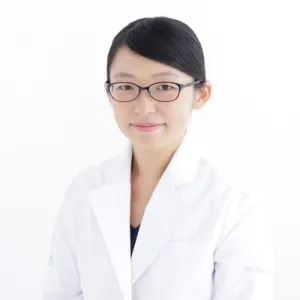
医師|木村 眞樹子(きむらまきこ)
都内大学病院、KDDIビルクリニックで循環器内科および内科に在勤。総合内科専門医・循環器内科専門医・日本睡眠学会専門医。産業医として企業の健康経営にも携わる。
自身の妊娠・出産、産業医の経験を経て、予防医学・未病の重要さと東洋医学に着目し、臨床の場でも西洋薬のメリットを生かしながら漢方の処方を行う。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でもサポートを行う。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)