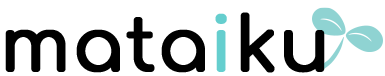シャッターが降りたままの店舗、寂れたアーケード、少ない人通り…そんな終わった印象を持たれがちな地方商店街ですが、香川県高松市にある「丸亀町商店街」は、そうした常識を見事に覆しました。
かつては衰退の象徴とまで言われたこの商店街が、いまや全国から視察が訪れるほどの再生モデルとして注目を集めています。
一体何が起きたのか?その背景には、行政にも真似できない、驚くほど戦略的で柔軟「町ちづくり」があったのです。
バブルと瀬戸大橋、人が消えた町

丸亀町商店街の衰退は、1990年代に入って一気に加速、ひとつの要因はバブル経済による地価の高騰でした。
当時、多くの商店主は「土地は資産だ」という銀行の言葉を信じ、こぞってマンション建設や土地購入に走ります。
結果としてバブル崩壊後には多額の負債だけが残り、商売とは関係のない借金に苦しむ事態となりました。
廃業したくても債務処理ができないという、まさに袋小路の状態、さらに1988年に瀬戸大橋が開通すると香川県内に大型店が続々と出店を始めます。
流通が劇的に変わり、買い物客は郊外のショッピングモールへと流れていき、丸亀町のアーケードは次第に人の姿を消し、店の灯りも落ちていきました。
まさに「シャッター商店街」と呼ばれるにふさわしい状況に至ったのです。
土地は売らないで町を変える
再開発と聞くと、土地の買収や行政主導の計画を思い浮かべる人が多いでしょう。
しかしこの商店街では、地権者が所有権を持ったまま、利用権のみを町づくり会社に貸し出すという「定期借地権方式」が採用されました。
つまり、土地は誰のものでもなくなったわけではありません。
ただ60年間という一定期間、町づくり会社がまとめて借りることで、再開発の自由度を確保したのです。
これにより、土地を売ることに抵抗のある地権者も参加しやすくなり、結果として街全体の設計に統一感を持たせることができました。
費用面でも、土地の買収が不要となったことで初期投資を大幅に抑えることができたのは大きな利点です。
こうした現実的かつ柔軟な制度設計が、再開発の実行可能性を高めた要因だと言えるでしょう。
商人から経営者へ
丸亀町の商店街では再開発にあたって、ほぼ全ての店舗がいったん廃業するという前代未聞の決断をしました。
商売人であった彼らが、土地と店の未来を自ら設計する「まちの経営者」へと変わったのです。
まちづくりのコンセプトは、「生活が戻ってくるまちにする」ことでした。
単に店を並べるのではなく、商業施設の上層階には高齢者向けの住宅を設置し、併設するかたちでクリニックや福祉施設も整備、さらに子育て世代を意識して、おもちゃ美術館などの施設も取り入れました。
かつて地価が高すぎて人が住めなくなったエリアに生活者を呼び戻す。それが街の再生に不可欠だと考えたのです。
結果として、5人しかいなかった居住人口は1000人以上に増え、通行量も驚くほど回復、何より商店街に必要な青果店や雑貨店、クリーニング屋など暮らしのための業種が再び根付いてきました。
再生の先にある持続可能な都市へ
こうした再開発の成果は、数字にも表れています。
地価は市内最高値を維持し、通行量は1日2万人超、商店街にはファッションブランドから飲食店まで多様なテナントが集まり賑わいが戻りました。
さらに、地域通貨「カメ」の導入も注目されています。
これはイベントやボランティアの謝礼として配られ、地域内で使えるクーポンのような役割を果たします。
人と消費を地域の中で循環させるという発想が、見えない部分でまちを支えています。
再開発で終わるのではなく、その先の暮らしをどう設計するか?丸亀町の事例は「都市を経営する」という視点がどれほど重要かを私たちに教えてくれます。
まとめ
丸亀町商店街の再生は、単なる建物の建て替えや補助金頼りの地域活性ではありませんでした。
地権者たちが自分たちの土地と未来に責任を持ち、まち全体を一つの「生活空間」として設計し直した結果です。
あきらめずに調べ、考え、動いた、民間が覚悟を持って未来に投資したその姿勢こそが、「再開発」という言葉の本質を体現しています。
今、日本全国には同じように悩みを抱える商店街が数え切れないほどあります。
そのすべてが丸亀町のようになれるとは限りませんが、ヒントは確かにここにあるのではないでしょうか。
あわせて読みたい|マタイク(mataiku)